ブランディングが必要ない企業、向かない企業とは?
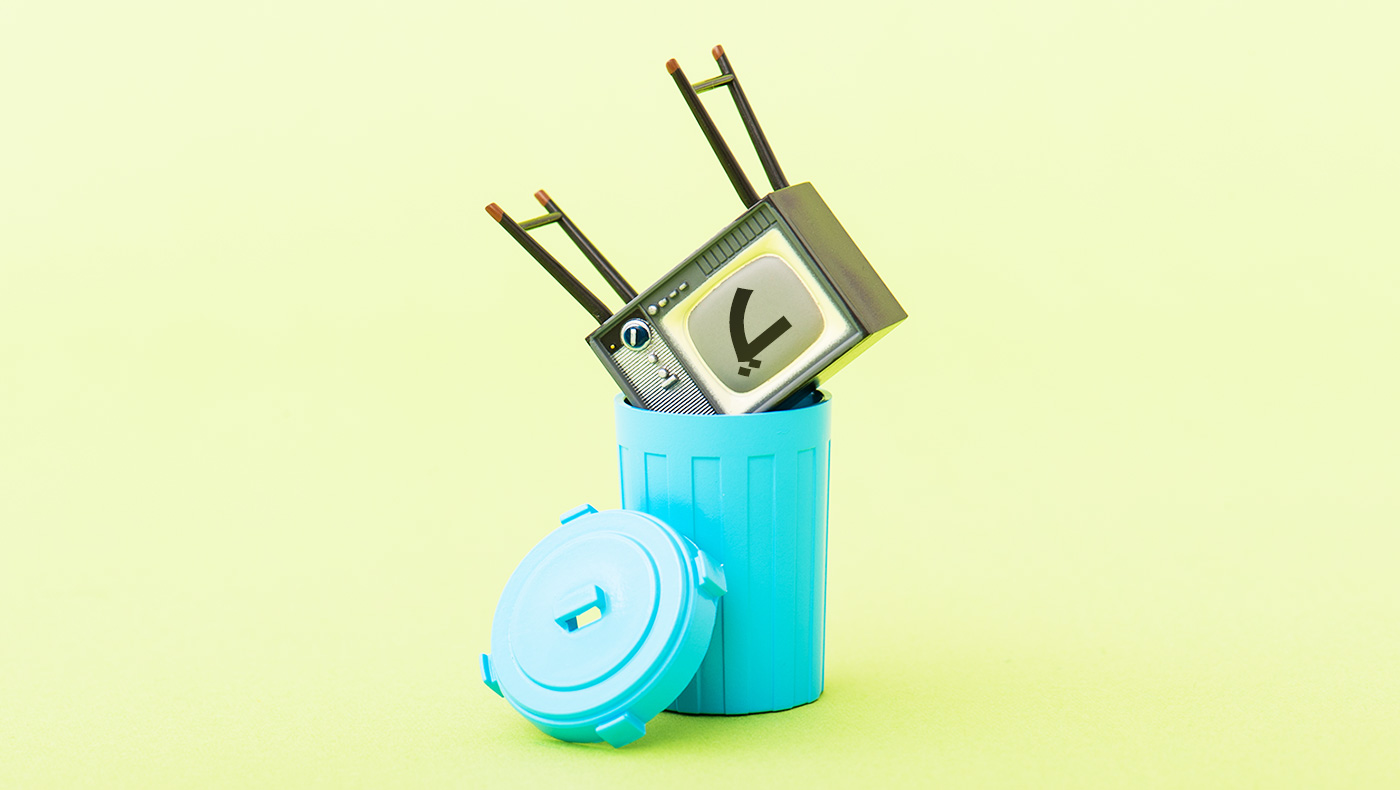
ブランディングが重要とはいうけれど自分の会社には必要ない気がする。そう考えている人も多いと思います。
一聞すると万能な施策に思われがちなブランディングですが、残念ながらそうではありません。
ブランディングが必要ない企業や向かない企業は結構あります。
そんな企業は他の解決策を選ばれた方がいい。
今日はそんな「必要のない」または「向かない」企業はどんな企業なのかを書きます。
必要のない企業とは
- 大手企業の子会社で、販売先がその親会社と決まっている企業
このタイプの企業は、原則的にマーケティングが必要ありません。
なぜなら販路を作り販売する必要がないからです。
さらにこのタイプの企業は買い手である大手の親会社のためにだけある企業です。
三菱や三井のような財閥系の超大手企業は、グループ会社内だけでお金が回るような仕組みになっていて、まるで一つの社会のように成り立っている上に、その社会の中で、子会社の製品を購する相手は親会社と決まっているので、もはやマーケティングの必要がない、ある意味とても恵まれた環境の会社です。
原則としてブランド力が必要とされる企業は買い手である顧客が自由に業者を選定できる状態にあるか否かです。
仮に現在他社が一社も参入していない市場に自社がいたとしても、いずれ誰かが参入してくる恐れがある状態では、ブランド力が高めておいたほうがいい。しかし、このタイプの企業の場合、買い手である親会社は他の業者を選ぶこともなく裏切らない取引関係にあります。
例えばカメラ業界のようにフィルムがなくなりデジタルに移行したことで、会社の存続が危ぶまれるような状況にない限り、ある意味においては保証された環境です。
こうした企業は例外はあるにしろ、大概はブランド力を必要としません。
インナーブランディングはどうか
ブランディングにはインナーブランディングといわれる種類のブランディングがあって、社内活性化に大いに貢献するとても重要なものです。しかし、これに関してもまず必要ありません。
なぜなら、インナーブランディングは社内活性化に貢献しますが、それだけが目的ではなく、その結果としてアウトプットにつなげる土台づくりが目的でもあるからです。
世間一般的な中小企業が置かれている状況とは間違いなく異なる環境の企業です。当然お客様に高品質なものを届けることは徹底していますが、理念というのものを経営に活かす必要があまりなく(というよりただのお題目になっているため)理念などの根底にある部分を活かした社内活性化や、アウトプットに繋げる土台づくりまで考えることはオーバースペックなのです。
マーケティングそのものが必要のない企業では、社内活性化だけにフォーカスするのであれば、社内イベントや福利厚生などの充実の方が、よほど重要になってきます。
ブランディングが必要になるケース
しかしこういった企業でもブランド力が必要になるケースがあります。
それは地域の人たちなど、特定の人たちとの関係構築が必要となるケースです。
大きい工場を建てたりすると地域の人たちとの信頼構築や、また良い人材を雇用するためにも、ブランディングが必要になるケースがあります。
なぜなら企業として信頼があり優良であるばかりでなく、ブランディングは何よりも、人から愛される企業を目指す施策だからです。
向かない企業

向かない企業は主に次の二つです。
- 中長期的視点に興味がなく単発的で瞬発力のある施策にしか興味をもてない企業
- とにかく儲かれば全て良しと考えている企業(反社会的意味ではなく)
中長期的視点に興味がなく単発的で瞬発力のある施策にしか興味をもてない企業
目先の利益や短期的施策にしか、目を向けられない体質の企業には向きません。
短期的効果しかなくてもかまわないから、目先の売り上げを確保しないとやばい、といった企業も多いと思います。
短期間の施策ばかり打っているだけでは自転車操業になってしまったり、マーケティングに費やす体力を持ち続けるのは困難で、本音をいえばブランド力を高めたい企業も多いはず。
あえてそこでブランディングを行う企業もあれば、まだ先延ばしにする企業もあります。
それらは単にプライオリティーの問題で、ブランディングを行うか行わないかの判断をしているにすぎませんが、
根本的な体質として、常にすぐ結果のでる施策にしか興味がない企業がいます。そういったタイプの企業はブランディングはなかなか向かない。
ブランディングという言葉は聞こえはいいですが、実際は地道に地道におこなっていく姿勢がとても必要とされる施策だからです。
とにかく儲かれば全て良しと考えている企業 (反社会的意味ではなく)
このタイプの企業には、向いている企業とそうでない企業があります。
お客様へちゃんと目線がいっている企業(向いている企業)
「儲かればすべて良し」というと一聞すると冷たい言葉に聞こえますが
言葉の裏には実はお客さまのことを徹底的に考えていたりします。
こんな感じに ↓↓↓
「儲かるというのは言い換えれば、お客さまのニーズを満たしていることであり、それはつまり、サービスや商品が世間から認められているということ。つまり儲かればすべて良しなんだ」
こんな考え方を持っている方は多くいらっしゃいます。
「儲かれば全て良し」の裏側にはプロ意識も強くもっている。
そんな企業はブランド力を高める底力をもっています。
文字通り儲かるだけを考えている企業(向かない企業)
一方で「儲かれば全て良し」という言葉の真意そのものが、儲け話や流行り物にばかり目がいってお客さまが見えていないような、文字通り儲かることしか考えていない企業は、ブランディングには向きません。
小手先のデザインや宣伝文句ばかりに目がいってしまったり、商品のインスタ映えばかりに目がいき、中身が伴わないサービスをしているようではブランディングはできないのです。
ブランディングにはお客さまを大切に考えていることが必要不可欠で、自社の利益のことしか目が行っていない企業にはブランディングはできません。
ブランドとは人から愛される商品や企業、そのものだからです。
ブランディングの要・不要、向き不向きは
規模や事業内容じゃない

ブランディングは昨今、どんな企業も注目している施策ではありますが、まだまだブランディングには誤った理解が広まっています。
その代表的な勘違いは、
- ブランディングはB to C事業社のためのものだ
- おしゃれにするものだ
- 大手企業のものだ
などです。
ですが、この記事を読み、気づいた方もいらっしゃると思いますが、一言も規模や業界については触れていません。
ブランディングの要不要、向き不向きは
- マーケティングが不要でも経営が確約されている特殊条件化にあるかどうか
- お客様を考えたサービスを、届けたい気持ちがあるかどうか
- 中長期的視点で取り組もうとするスタンスがあるかないか
原則この計3点に作用されます。
その他、企業に置かれている状況によってブランディングを優先すべきか、それとも他の解決策を優先すべきかは変わってきます。
ブランディングはどんなジャンルでも活用できるものです。
自分の会社なんて、、、と思うのは不要です。もし、ご自身の会社が上記に当てはまらないと思うのであれば、一度検討してみる価値は多いにあります。
とはいえ、ブランディングは数ある戦略の一つでしかありません。
企業のカルチャーを考えること。それが何よりも大切だと僕は思っています。
伝わらず、
価値が理解されない
そんな課題感を
お持ちのみなさまへ
コードマークはブランディングデザインの手法を用い、企業のみなさまの意志を深く理解したうえで、貴社にフィットした制作物、制作プロセスのご提案をいたします。

Services
そんな課題感をお持ちのみなさまへ
コードマークはブランディングデザインの手法を用い、
企業のみなさまの意志を深く理解したうえで、
貴社にフィットした制作物、制作プロセスのご提案をいたします。

Services